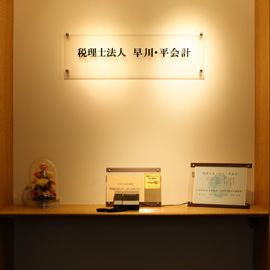自分で相続税申告はできる?税理士に依頼するメリットも解説
相続が発生すると、税務署への申告が必要になる場合があります。
専門知識が多く求められるため、基本的には税理士に依頼するひとが多数派です。
しかし依頼費用がかかることから「税理士に依頼せず自分で申告したい」と悩む方も少なくありません。
今回は、自分で相続税申告が可能なのか、その判断基準や注意点を解説します。
相続税申告が必要となるケース
相続税は、一定額を超える財産を相続した場合に課される税金です。
相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の総額によって決まります。
具体的には、課税対象となる財産が、基礎控除額を超えた場合に申告が必要です。
基礎控除の仕組み
相続税には、誰でも使える「基礎控除」があります。
基礎控除の金額は、以下の式で計算されます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人いる場合の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×3=4,800万円」です。
申告が必要となる財産とは
申告対象となる財産には、以下のようなものが含まれます。
- 不動産(土地・建物)
- 預貯金や株式などの金融資産
- 生命保険金(一定額を超える部分)
- 贈与財産(一定期間内のもの)
上記を合計し、合計額が前述の基礎控除額を上回る場合は、原則として申告が必要です。
相続税申告を自分で行えるか
結論、制度上の話で考えれば、相続税申告は自分だけでも行えます。
財務省「令和5事務年度国税庁実績評価書」によれば、相続税の申告に税理士が関わっている割合は例年85%程度です(令和元年~令和5年まで)。
つまり、15%程度のひとは、毎年自力で申告している計算になります。
「自分で申告できる可能性があるケース」「自分での申告が難しいケース」をよく理解して、慎重に判断してください。
自分で申告できる可能性があるケース
以下のようなケースであれば、自分で申告できる可能性があります。
- 相続人が少数で、相続関係が単純
- 財産の内容が現金や預貯金に限られている
- 特例の適用を必要としない
- 遺産分割がすでに円満に成立している
自分で申告する際の障害になるのは、複雑な手続きをしなければならないことです。
そうした事情がなく、相続税に関する知識を十分に持っている場合は、自分の力だけでも手続きを進められる可能性があります。
自分での申告が難しいケース
一方で、以下のようなケースでは専門家への依頼が一般的です。
- 相続財産に不動産が含まれている
- 小規模宅地等の特例を適用する予定がある
- 複数の相続人間で意見の不一致がある
- 生前贈与など複雑な取引が含まれている
不動産は現金や預金とは異なり、評価の方法や分け方など難しい部分が多くあり、一筋縄ではいきません。
特例の適用に関しても、厳密な条件が設定されており、手続きが大変です。
一見して複雑だと思われるような相続は、基本的に自力で解決しようとはせず、税理士などの専門家の手に委ねるのが無難です。
自分で申告するために必要な準備
相続税申告を自分で行う場合は、事前準備が重要です。
以下のステップに沿って進めれば、ミスを防ぎやすくなります。
- 必要書類の収集
- 財産評価と相続税額の計算
- 申告書の作成・提出
相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。
期限を過ぎると、加算税や延滞税が課される可能性があります。
税理士に依頼するメリット
自分で申告するのが不安な場合や、手続きが煩雑な場合は、税理士に依頼するのがおすすめです。
主に以下のようなメリットがあります。
- 財産評価や申告書作成を任せられる
- 特例の適用など節税対策をしてもらえる
- 税務調査に備えた対応がしやすくなる
- 申告ミスによるペナルティリスクを軽減できる
それぞれ確認していきましょう。
財産評価や申告書作成を任せられる
相続税申告で最も労力がかかるのが、財産評価や申告書類の作成です。
土地や建物の評価には「路線価」や「倍率方式」などの専門知識が求められ、誤った評価を行うと過大または過少な税額になるリスクがあります。
税理士に依頼すれば、相続税に関する一連の作業を代行してもらえるため、手間を大きく削減できます。
特例の適用など節税対策をしてもらえる
相続税には、税負担を軽減するための特例制度がいくつもありますが、それぞれに細かな適用条件があります。
税理士はさまざまな条件を熟知しており、財産内容や家族構成に応じて、最も有利な制度を選択しつつ適切に申告を進めてくれます。
税務調査に備えた対応がしやすくなる
所得税や法人税などと同様、相続税の申告後は、税務署から調査が入る可能性があります。
特に以下のようなケースでは、調査が行われやすい傾向があるため注意が必要です。
- 名義預金や現金の申告漏れが疑われる
- 土地の評価が著しく低い
- 申告内容に不明点がある
税理士が関与していれば、税務署とのやり取りや調査への対応も任せられるため、相続人自身の負担を大きく減らせます。
申告ミスによるペナルティリスクを軽減できる
相続税申告には、期限や記載ミスに対して厳格な取り扱いがなされます。
- 申告漏れによる過少申告加算税
- 申告遅れによる無申告加算税
- 納付遅れによる延滞税
税理士に依頼すれば、上記のような申告上のミスや、手続き漏れを未然に防げます。
まとめ
相続税申告は制度上、自分で行えます。
財産の構成が単純で、特例の適用が不要な場合は、自力での申告も視野に入ります。
しかし不動産や特例の利用、遺産分割協議の難航などがある場合は、税理士への依頼を検討してください。
無理をせず、自分に合った方法を選ぶのが重要です。
当事務所が提供する基礎知識
BASIC KNOWLEDGE
-

自分で相続税申告はで...
相続が発生すると、税務署への申告が必要になる場合があります。専門知識が多く求められるため、基本的には税理士に依頼するひとが多数派です。しかし依頼費用がかかることから「税理士に依頼せず自分で申告したい」と悩む方も少なくあり […]
-

家族に会社を承継する...
日本の中小企業では、経営者の高齢化が進み、多くの企業が「誰に事業を引き継ぐか」という課題を抱えています。中でも、最も一般的な方法が、家族、つまり親族内での事業承継です。しかし、実際に承継を行うには多くの準備と手続きが必要 […]
-

事業承継は早目の対策...
◆事業承継は早目の対策が重要!経営や事業の承継というのはすぐにできるものではありません。円滑な事業継承を実現するのは、早めの対策が非常に重要です。事業経営を行っておられる場合は、問題を後回しにせずに是非早目にお問合せ下さ […]
-

相続税問題を税理士に...
相続が発生すると、まず直面するのが「相続税」の問題です。財産の評価や相続税の申告・納税など、やらなければならないことが多く、専門知識がないまま進めると思わぬトラブルに発展する可能性もあります。そこでおすすめなのが、税理士 […]
-

相続税の計算方法とは...
相続が発生した場合、ある一定の範囲を超えると相続税を支払う必要があります。今回は相続税の計算方法や、基礎控除額などについて詳しく解説していきたいと思います。相続税は最大税率55パーセント相続税は累進課税制度が採用されてい […]
-

税理士法人早川・平会...
◆経験豊富で相続に強いスタッフが在籍しています!当事務所では相談や依頼を含め、年間120件以上の相続案件を取り扱っております。経験豊富な実績をもとに、さまざまなケースに素早く対応させていただけます。スタッフも相続専門また […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
年間120件の相続相談をこなす『相続特化型』税理士事務所です。
ご安心してお問合せ下さい

-
- 所属団体
- 東京税理士会神田支部
-
- 経歴
-
1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
事務所概要
OFFICE
| 事務所名 | 税理士法人早川・平会計 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田司町2-10安和司町ビル2F |
| 電話番号 | 03-3254-2171 |
| FAX番号 | 03-3254-2174 |
| 受付時間 | 9:00~18:00 (ご予約により時間外対応可) |
| 定休日 | 土・日・祝 (ご予約により休日対応可) |
| URL |