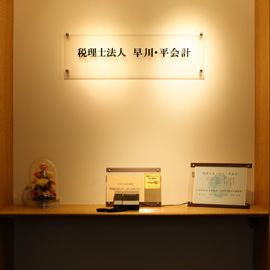不動産評価額に関わる路線価とは?
不動産を相続する際、その評価額を決定する重要な基準のひとつが「路線価」です。
路線価を正しく理解し、評価額を適切に算出することは、相続税の計算を行ううえで欠かせません。
今回は、路線価の基本的な仕組みや使い方、注意点について解説します。
路線価とは何か
路線価とは、国税庁が公表する土地の評価額を示す指標です。
特定の道路に面する土地1平方メートルあたりの価額が設定されており、これを基にして土地の相続税評価額が計算されます。
路線価は、主に市街地や住宅地の土地評価に用いられ、毎年1月1日時点の価格が7月ごろに発表されます。
公示地価との違い
路線価と公示地価は混同されがちですが、それぞれの目的と算出方法が異なります。
公示地価は国土交通省が土地取引の指標として算出する価格で、土地の取引価格に近い値が設定されます。
一方、路線価は相続税や贈与税の計算のために利用される価格で、公示地価のおおよそ8割程度の水準で設定されています。
補正率による調整
路線価は土地の面する道路ごとに設定されていますが、土地の形状や利用状況によって評価額が異なる場合があります。
たとえば、不整形な土地や奥まった場所にある土地などは、その条件に応じて補正率を適用して評価額を調整します。
これにより、実際の土地価値に近い評価が可能になります。
路線価の調べ方
路線価は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」から確認することができます。
このツールを活用すれば、特定の土地がどの程度の評価額を持つのか、簡単に調べることができます。
路線価図の見方
路線価図は、市町村ごとに道路沿いの路線価が記載された地図です。
数字とアルファベットで構成される記号が記載されており、たとえば「200E」とあれば、その道路に面する土地の評価額は1平方メートルあたり20万円であることを意味します。
数字は千円単位の表示です。
アルファベットは「借地権割合」を示しており、借地権の評価に用いられます。
借地権とは、借主が土地を使用する権利を指します。
一方で、借地権割合は、土地の価格に対して借地権がどの程度の割合を占めるかを数値化したものです。
評価額の計算方法
土地の評価額は、路線価に土地面積を掛け算することで求められます。
たとえば、路線価が20万円で、面積が100平方メートルの土地の場合、評価額は20万円×100平方メートル=2,000万円となります。
ただし、土地の形状や利用状況に応じて補正率を適用する場合があるため、最終的な評価額には注意が必要です。
路線価の利用上の注意点
路線価は便利な指標ですが、利用する際にはいくつかの注意点があります。
路線価が設定されていない場合
一部の地域では、路線価が設定されていない場合があります。
その場合は、「評価倍率表」を利用して土地の固定資産税評価額を基に評価額を算出します。
たとえば、150㎡の住宅用地があり、1㎡あたりの固定資産税評価額が10万円、評価倍率が1.1倍の場合の評価額は、150㎡ × 10万円 × 1.1 = 1,650万円となります。
固定資産税評価額は、毎年1月1日時点で土地の所有者に送付される「固定資産税課税明細書」や、土地の所在地の自治体で取得できる「固定資産評価証明書」で確認できます。
評価倍率表は国税庁のホームページで公開されており、地域や用途ごとに異なります。
補正率の確認が必要
土地の形状や立地条件によって補正率が適用される場合、正しい補正率を把握することが必要となります。
路線価の補正には、奥行価格補正、不整形地補正、間口狭小補正、奥行長大補正、がけ地補正などが含まれます。
各補正率の詳細については、国税庁のホームページに掲載されている財産評価基本通達や調整率表で確認することができます。
補正率の適用を誤ると、評価額が適切に算出されず、結果として相続税額に影響を与えるためしっかりと確認する必要があります。
市場価格との差異
路線価は市場価格の目安にはなりません。
市場価格は需要と供給によって決まるため、路線価よりも高い場合や低い場合があります。
そのため、相続後の不動産売却を検討している場合は、市場価格もあわせて確認しましょう。
まとめ
路線価は、不動産の評価額を決める際に重要な基準となります。
正しく理解し活用することで、相続税の計算を効率的かつ適切に進めることができます。
ただし、補正率の適用や評価額の計算は専門的な知識を必要とする場合もあります。
相続税の計算や土地評価で不明点がある場合は、税理士に相談することを検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
BASIC KNOWLEDGE
-

親族外承継を行うとき...
相続や事業承継の場面では、後継者が必ずしも家族であるとは限りません。近年では、社員や社外の経営者、M&Aによる第三者への承継も増えています。しかし、家族以外の後継者に承継する場合は、親族承継とは異なる課題や注意点 […]
-

税務調査されるケース...
◆課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースは特に注意特に、課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースについては、被相続人の自宅に行って調査(臨宅調査)があります。臨宅調査は、通常、申告・納税した年または […]
-

税理士法人早川・平会...
◆経験豊富で相続に強いスタッフが在籍しています!当事務所では相談や依頼を含め、年間120件以上の相続案件を取り扱っております。経験豊富な実績をもとに、さまざまなケースに素早く対応させていただけます。スタッフも相続専門また […]
-

相続税いくらまでなら...
相続が発生すると、相続財産の規模によっては相続税が課されることがあります。 しかし、一定の基準以下の財産であれば相続税の申告は不要です。 今回は、相続税がいくらまでなら申告不要なのか、その基準や計算方法について詳しく解説 […]
-

相続税対策はなぜ必要...
しっかりとした相続税対策を行わなかったために、納税資金を確保するために相続した不動産の売却をする事態になってしまったり、相続税を納付するために多額の借入をするケースも多々あります。自宅不動産を売却する事態になれば、当然転 […]
-

法人向けの節税対策
法人向けの節税対策としては、以下のものがあります。■課税対象額を減らす税金は課税対象となる益金に、一定の税率が課せられるものですから、益金を減らせば当然税金を減らすことが可能です。例えば、役員報酬を増やすことによって、会 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
年間120件の相続相談をこなす『相続特化型』税理士事務所です。
ご安心してお問合せ下さい

-
- 所属団体
- 東京税理士会神田支部
-
- 経歴
-
1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
事務所概要
OFFICE
| 事務所名 | 税理士法人早川・平会計 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田司町2-10安和司町ビル2F |
| 電話番号 | 03-3254-2171 |
| FAX番号 | 03-3254-2174 |
| 受付時間 | 9:00~18:00 (ご予約により時間外対応可) |
| 定休日 | 土・日・祝 (ご予約により休日対応可) |
| URL |