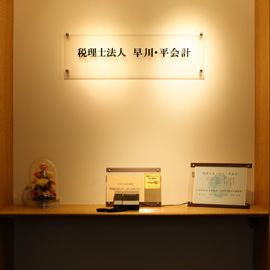相続税の計算方法とは?基礎控除額などについて解説
相続が発生した場合、ある一定の範囲を超えると相続税を支払う必要があります。
今回は相続税の計算方法や、基礎控除額などについて詳しく解説していきたいと思います。
相続税は最大税率55パーセント
相続税は累進課税制度が採用されています。
累進課税制度とは、金額に応じて税率が上がることをいい、課税所得に対し10パーセントから最大55パーセントまでになります。
相続税は、贈与税とならんで非常に高い税率がかけられることになります。
相続税の課税対象となるのは債務を差し引いた額
相続税は遺産総額から借金などの債務を差し引いた額が、課税対象額となります。
そのため貯金が10億円あったとしても、債務が多ければ、相続税の支払いが生じなかったり、発生しても低い金額ですんだりすることもあります。
ただし、遺産から差し引ける債務は、基本的に被相続人の生前に発生していた債務のうち、支払いが確実になるものに限られます。
支払いするかどうかがあいまいな債務に関しては、プラスの遺産から差し引くことができないため注意が必要です。
なお例外的に、相続が発生した後であってもお通夜や告別式などにかかった費用に関しては債務として算入することができます。
とはいえ算入できる費用は、社会通念上一般的であるという範囲に限定されています。
盛大な葬式を行ったとして、すべての費用が控除されるわけではありませんので注意しましょう。
相続税の基礎控除額の計算方法
相続税には、基礎控除額というものが設定されており、次のように計算することができます。
■基礎控除額の計算式
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
上記の計算式を確認するとわかるとおり、法定相続人の数によって基礎控除額が大きく左右されるため、正確に把握することが大切です。
法定相続人とは、被相続人と以下のような続柄のことを指し、相続における優先順位も法律によって決められています。
配偶者は必ず相続人になることができる
被相続人の配偶者は必ず相続人になります。
たとえ、別居していたとしても法的に夫婦である状態ならば、相続人になることが可能です。
一方、事実婚など法律上の夫婦ではない場合には、同居期間が長く、実質法定婚の夫婦と変わらない関係だったとしても相続人になることができません。
相続第1順位:子どもなどの直系卑属
配偶者以外の相続人には優先順位があり、最も優先されるのが、子どもなどの直系卑属です。
直系卑属とは、被相続人の直系の子孫のことを指します。
子どもが相続発生前に亡くなっており、孫がいる場合には、その孫が相続人になります。
相続第2順位:父母などの直系尊属
被相続人に子どもがいない場合、相続第2順位の父母などの直系尊属が相続人になります。
直系尊属とは、被相続人の直系の祖先のことをさします。
相続第3順位:兄弟姉妹などの傍系血族
被相続人の子どもや親がいない場合、兄弟姉妹などの傍系血族が相続人になります。
相続税の計算の具体例を紹介
相続税の計算について具体例を交えて紹介していきたいと思います。
ケース①課税所得が2億円で被相続人に配偶者・子ども2人・両親がいる場合
今回のケースの場合、債務などを差し引いた課税所得が2億円です。
被相続人には配偶者、子ども、両親がいる場合、相続人となれるのは配偶者と相続第1順位の子ども2人であるため、法定相続人は3人になります。
■基礎控除額
3000万円+(600万円×3)=4800万円
■相続税の対象となる金額
2億円-4800万円=1億5200万円
課税対象の遺産を相続人である配偶者と子ども2人が法定相続分(※)で分けた場合の取り分は以下になります。
配偶者の取り分:1億5200万円×2分の1=7600万円
子ども1人当たりの取り分:7600万円÷2=3800万円
※配偶者と子どもの法定相続分は遺産の2分の1ずつとなります。子どもが複数いる場合には、割り当てられた遺産を子どもの人数で割ります。
■配偶者と子どもが支払う相続税
相続税は遺産の取得分の金額に応じて税率が決まります。
配偶者の場合、7600万円を取得したので、相続税の税率は30パーセントとなります。
子どもは1人あたり3800万円を取得したので、相続税の税率は20パーセントです。
これらを計算すると配偶者と、子ども1人当たりの相続税は次のように計算できます。
配偶者:7600万円×30パーセント‐700万円(控除額)=1580万円
子ども(1人あたり):3800万円×20パーセント‐200万円(控除額)=560万円
今回のケースでは、相続人全員で支払う相続税額は合計2,700万円になります。
この合計額を相続する財産の割合で按分して相続人が支払をすることになります。
まとめ
今回は、相続税の計算方法や、基礎控除額などについて解説していきました。
相続税の計算は、相続財産の種類や金額が高くなるほど複雑になります。
また、今回ご紹介した基礎控除の他にも利用できる、控除や特例があるので、支払う相続税をなるべく抑えたいと考えたときには、税理士へ相談してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
BASIC KNOWLEDGE
-

不動産の購入は相続税...
現金や預貯金は、その金額がそのまま相続税の評価額となります。一方、不動産は評価額の算出方法や特例などがあるため、購入することで相続税対策になる場合があります。この記事では、不動産がなぜ相続税対策になるのか、そして不動産の […]
-

相続税対策はなぜ必要...
しっかりとした相続税対策を行わなかったために、納税資金を確保するために相続した不動産の売却をする事態になってしまったり、相続税を納付するために多額の借入をするケースも多々あります。自宅不動産を売却する事態になれば、当然転 […]
-

相続税いくらまでなら...
相続が発生すると、相続財産の規模によっては相続税が課されることがあります。 しかし、一定の基準以下の財産であれば相続税の申告は不要です。 今回は、相続税がいくらまでなら申告不要なのか、その基準や計算方法について詳しく解説 […]
-

親族外承継を行うとき...
相続や事業承継の場面では、後継者が必ずしも家族であるとは限りません。近年では、社員や社外の経営者、M&Aによる第三者への承継も増えています。しかし、家族以外の後継者に承継する場合は、親族承継とは異なる課題や注意点 […]
-

セカンドオピニオン
◆税務におけるセカンドオピニオンとはセカンドオピニオンとは顧問税理士の判断以外に、他の税理士の意見を求めるサービスのことを言います。相続の手続きの最中に、いま依頼している税理士が行った土地の評価は正しいのか、分割の割合は […]
-

事業承継税制はどんな...
会社を後継者へと引き継ぐ事業承継ですが、黒字であっても事業承継ができずに廃業となってしまうことがしばしばあります。円滑な事業承継を妨げている要因はさまざまです。例えば少子高齢化によってそもそも後継者となる者がいないことも […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
年間120件の相続相談をこなす『相続特化型』税理士事務所です。
ご安心してお問合せ下さい

-
- 所属団体
- 東京税理士会神田支部
-
- 経歴
-
1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
事務所概要
OFFICE
| 事務所名 | 税理士法人早川・平会計 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田司町2-10安和司町ビル2F |
| 電話番号 | 03-3254-2171 |
| FAX番号 | 03-3254-2174 |
| 受付時間 | 9:00~18:00 (ご予約により時間外対応可) |
| 定休日 | 土・日・祝 (ご予約により休日対応可) |
| URL |