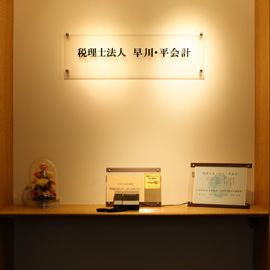不動産を相続する場合の評価方法は?
不動産を相続した際、相続税や登録免許税といった複数の税金が発生します。
しかし、これらの税金がどのように計算されるのか、また、どうすれば税金の負担を軽減できるのか、その仕組みは複雑でわかりにくいものです。
この記事では、不動産の相続税評価額の計算方法と、相続で不動産を取得する場合の注意点について解説いたします。
相続で不動産を取得した場合の評価方法
不動産を相続した場合、その評価額は時価ではなく、相続税法で定められた独自の基準に基づいて計算します。
この評価額は、相続税の総額を決定する上で非常に重要になります。
不動産の評価額は、土地と建物それぞれ別々に計算する必要がある点に注意が必要です。
土地は国税庁が定める評価基準を基に計算され、建物は固定資産税の評価額を基に計算されます。
それぞれの評価方法について確認していきましょう。
土地の場合
土地の評価には、主に路線価方式と倍率方式の2つの方法が用いられます。
路線価方式は、主に市街地の道路に面した土地に適用されます。
路線価とは、その道路に面する宅地の1平方メートルあたりの評価額であり、この路線価に土地の面積や形状に応じた補正率をかけて評価額を算出します。
一方、倍率方式は、路線価が定められていない郊外などの地域に適用されます。
これは、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出する方法です。
建物の場合
建物の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額をそのまま使用します。
固定資産税評価額は、各市町村が定める基準に基づいて算出されています。
その基準とは、総務省が定める「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準として、建物の構造や築年数による経年減点補正などを考慮して決定されます。
建物の評価は、土地の評価ほど複雑ではありませんが、適正な評価額を確認するためには、市町村役場で固定資産税評価証明書を取得する必要があります。
相続で不動産を取得する場合の注意点
不動産を相続する際には、後々のトラブルや予期せぬ出費を避けるために、いくつかの点に注意が必要です。
土地形状などによっては評価が難しくなる
土地の形状が複雑な場合や、傾斜地、不整形地、利用制限がある土地などは、評価が難しくなります。
評価額を算定する際に、奥行価格補正や不整形地補正といった様々な補正率を適用する必要があるためです。
これらの補正を適用することで、土地の評価額は大幅に減額される可能性があります。
しかし、専門的な知識がないと、これらの補正を適切に適用することが難しくなります。
相続人以外が不動産を取得した場合不動産取得税がかかる
不動産を相続によって取得した場合、原則として不動産取得税はかかりません。
しかし、相続人以外の人、たとえば遺言によって財産を取得する受遺者や、特別縁故者が不動産を取得した場合は、不動産取得税が課税されます。
不動産取得税は、不動産の取得時に1度だけかかる税金であり、その税額は固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算されます。
相続時精算課税を利用した不動産は特例が利用できない
相続時精算課税制度を利用して生前に不動産の贈与を受けていた場合、その不動産は相続財産に持ち戻されて相続税の課税対象となります。
この場合、小規模宅地等の特例などの特定の相続税の特例は利用できません。
小規模宅地等の特例は、居住用宅地の評価額を最大80%減額できる非常に有効な節税制度ですが、相続時精算課税制度を利用した不動産には適用されないため、注意が必要です。
不動産を相続した場合に税理士へ依頼するメリット
不動産を相続した場合、税理士へ依頼することには多くのメリットがあります。
税理士は、複雑な不動産の評価を正確に行い、相続税の申告を適切に行うことができます。 特に、土地の評価において、各種補正率を漏れなく適用することで、評価額を適正に抑え、節税につなげることができます。
また、小規模宅地等の特例など、専門的な知識が必要な特例の適用を見落とすことなく、最大限に活用できます。
まとめ
不動産の相続税評価額は、土地と建物を別々に計算する必要があり、評価方法が複雑です。
評価を誤ると、多くの相続税を支払うことになる可能性があります。
相続時精算課税制度を利用した不動産には特例が利用できないなど、注意点も多く存在します。
適切な評価と節税を行うためには、専門家である税理士に相談することが大切です。
不動産の相続でお困りの際は、ぜひ税理士にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
BASIC KNOWLEDGE
-

事業承継は早目の対策...
◆事業承継は早目の対策が重要!経営や事業の承継というのはすぐにできるものではありません。円滑な事業継承を実現するのは、早めの対策が非常に重要です。事業経営を行っておられる場合は、問題を後回しにせずに是非早目にお問合せ下さ […]
-

自分で相続税申告はで...
相続が発生すると、税務署への申告が必要になる場合があります。専門知識が多く求められるため、基本的には税理士に依頼するひとが多数派です。しかし依頼費用がかかることから「税理士に依頼せず自分で申告したい」と悩む方も少なくあり […]
-

養子縁組による相続税...
養子縁組をすることによる効果としてはまず相続税の軽減効果があります。(1)基礎控除額の増加(2)生命保険金の非課税金額の増加(3)退職手当金等の非課税金額の増加(4)相続税の総額の計算上をする上で累進税率が緩和される民法 […]
-

不動産を相続する場合...
不動産を相続した際、相続税や登録免許税といった複数の税金が発生します。しかし、これらの税金がどのように計算されるのか、また、どうすれば税金の負担を軽減できるのか、その仕組みは複雑でわかりにくいものです。この記事では、不動 […]
-

相続時精算課税制度の...
相続時精算課税制度は、生前贈与を活用する際に利用できる税制のひとつです。贈与税の負担を軽減しつつ財産を移転できる一方、注意点やデメリットもあるため、制度を正しく理解して活用することが重要です。今回は、相続時精算課税制度の […]
-

セカンドオピニオン
◆税務におけるセカンドオピニオンとはセカンドオピニオンとは顧問税理士の判断以外に、他の税理士の意見を求めるサービスのことを言います。相続の手続きの最中に、いま依頼している税理士が行った土地の評価は正しいのか、分割の割合は […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
年間120件の相続相談をこなす『相続特化型』税理士事務所です。
ご安心してお問合せ下さい

-
- 所属団体
- 東京税理士会神田支部
-
- 経歴
-
1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
事務所概要
OFFICE
| 事務所名 | 税理士法人早川・平会計 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田司町2-10安和司町ビル2F |
| 電話番号 | 03-3254-2171 |
| FAX番号 | 03-3254-2174 |
| 受付時間 | 9:00~18:00 (ご予約により時間外対応可) |
| 定休日 | 土・日・祝 (ご予約により休日対応可) |
| URL |