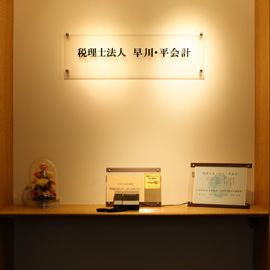持ち戻し期間7年で暦年贈与はどう変わる?
相続や贈与をめぐる税制は近年大きく変化しています。
なかでも注目すべきは、暦年贈与の「持ち戻し期間」が従来の3年から7年へ延長された点です。
本記事では、持ち戻し期間延長の概要や注意点、対策などについて解説します。
暦年贈与の持ち戻しの概要と改正内容
まずは、暦年贈与の持ち戻し制度の概要と、今回の改正内容について整理します。
暦年贈与の持ち戻しとは
相続が発生した際、被相続人が相続開始の直前に行った暦年贈与は「持ち戻し」の対象となり、相続財産に含めて計算する必要があります。
加算された贈与財産に対応する贈与税額は、相続税計算上で控除されます。
加算対象となる財産
加算の対象は、被相続人から暦年課税で贈与された財産のうち、加算対象期間内に贈与されたすべての財産です。
贈与税の有無に関わらず、基礎控除110万円以下の贈与や、被相続人が亡くなった年に行われた贈与も加算されます。
加算対象期間の改正
従来は「死亡前3年以内の贈与」が加算対象でしたが、税制改正により2024年(令和6年)以降の相続からは「7年」に延長されます。
この延長により、相続税対策としての暦年贈与は、これまで以上に早い段階から計画的に開始する必要が生じています。
暦年贈与とは?
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの間に受けた贈与額に対し、基礎控除(110万円)が適用される制度です。
基礎控除内であれば贈与税はかかりません。
例えば毎年110万円を10年間贈与すれば、合計1100万円を非課税で移転可能です。
しかし、持ち戻し期間延長により、死亡前7年間の贈与は相続財産に加算されるため、従来よりも非課税で移転できる額は事実上減る可能性があります。
なぜ暦年贈与は持ち戻し対象となるのか?
暦年贈与は広く利用されている制度ですが、持ち戻し制度の目的は「相続人間の公平性」と「課税の適正化」にあります。
もし相続人の一部が長期間にわたって贈与を受けていた場合、他の相続人との間で不公平が生じる可能性があります。
また、死亡直前に駆け込みで多額の贈与を行い、相続税負担を不当に軽減することを防ぐ狙いもあります。
持ち戻し期間延長に関する注意点
持ち戻し期間延長に関する主な注意点として、以下が挙げられます。
段階的に延長される
持ち戻し期間の延長は、2024年から一気に7年へ移行するのではなく、段階的に適用されます。
2027年以降の相続では、まず「死亡前4年以内の贈与」が対象となり、その後は5年6年と毎年1年ずつ延びて、最終的に2031年以降の相続から7年に達します。
延長部分の100万円までは非加算
延長された4年間分(3年から7年への延長部分)の贈与については、総額100万円まで相続財産に加算されません。
このため、延長期間に該当する贈与であっても、一定額までは課税対象外となりますが、それ以上の金額は相続財産に加算される点に注意が必要です。
持ち戻し期間延長への対策
持ち戻し期間延長への対策としては、主に以下が挙げられます。
1. 早期贈与で持ち戻し対象外にする
相続開始の8年以上前に贈与を済ませれば、持ち戻し対象から外れます。
早期に贈与を開始し、非課税枠(年間110万円)を活用することが重要となります。
2. 長期分割による贈与税率の抑制
贈与税は累進課税であり、一度に多額の贈与を行うと高税率が適用されます。
贈与を行う場合、複数年に分けて少額ずつ贈与すれば、毎年低い税率や非課税枠を利用でき、全体の税負担を軽減できます。
3. 相続時精算課税制度の活用
暦年贈与の持ち戻し延長に伴い、相続時精算課税制度の利用も検討できます。
この制度では、贈与財産の累計が2500万円までの部分は贈与税が非課税となります。
さらに、現在では、年間110万円までの非課税枠が追加されており、この枠内の贈与は相続時に加算されないため、節税効果が期待できます。
また、贈与を受けた人がその後に贈与者の相続人となった場合は、非課税枠を除く贈与財産を相続財産に加算して、相続税を計算・精算する仕組みとなっています。
なお、相続時精算課税と暦年課税は併用できず、一度相続時精算課税を選択すると暦年課税へ戻せないため、慎重な検討が必要です。
まとめ
持ち戻し期間の7年への延長は、生前贈与を活用した相続税対策の自由度を大きく制限します。
暦年贈与はできるだけ早く始めることが重要で、ケースによっては相続時精算課税制度の活用が有効となる場合があります。
贈与や相続に関してお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
BASIC KNOWLEDGE
-

法人向けの節税対策
法人向けの節税対策としては、以下のものがあります。■課税対象額を減らす税金は課税対象となる益金に、一定の税率が課せられるものですから、益金を減らせば当然税金を減らすことが可能です。例えば、役員報酬を増やすことによって、会 […]
-

持ち戻し期間7年で暦...
相続や贈与をめぐる税制は近年大きく変化しています。なかでも注目すべきは、暦年贈与の「持ち戻し期間」が従来の3年から7年へ延長された点です。本記事では、持ち戻し期間延長の概要や注意点、対策などについて解説します。暦年贈与の […]
-

税務調査とは?調査の...
法人税や所得税、消費税や相続税といった税金は、納税者自らが計算をおこない申告する「申告納税制度」が採用されています。そのため、税務署は納税者立ち合いのもと、納税者の税務申告内容を確認し、適切な経理処理のもとで正しく納税が […]
-

相続税問題を税理士に...
相続が発生すると、まず直面するのが「相続税」の問題です。財産の評価や相続税の申告・納税など、やらなければならないことが多く、専門知識がないまま進めると思わぬトラブルに発展する可能性もあります。そこでおすすめなのが、税理士 […]
-

税務調査されるケース...
◆課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースは特に注意特に、課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースについては、被相続人の自宅に行って調査(臨宅調査)があります。臨宅調査は、通常、申告・納税した年または […]
-

事業承継税制とは?
中小企業の多くが経営者の高齢化と後継者不足という課題に直面しています。事業を次の世代に引き継ぐ際、相続税や贈与税の負担が大きな障壁となるケースも少なくありません。こうした中、税制面から事業承継を後押しする「事業承継税制」 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
年間120件の相続相談をこなす『相続特化型』税理士事務所です。
ご安心してお問合せ下さい

-
- 所属団体
- 東京税理士会神田支部
-
- 経歴
-
1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
事務所概要
OFFICE
| 事務所名 | 税理士法人早川・平会計 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田司町2-10安和司町ビル2F |
| 電話番号 | 03-3254-2171 |
| FAX番号 | 03-3254-2174 |
| 受付時間 | 9:00~18:00 (ご予約により時間外対応可) |
| 定休日 | 土・日・祝 (ご予約により休日対応可) |
| URL |