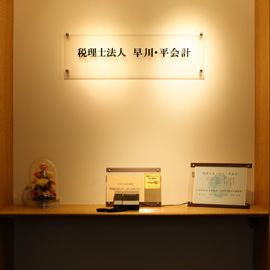家族に会社を承継する方法とは
日本の中小企業では、経営者の高齢化が進み、多くの企業が「誰に事業を引き継ぐか」という課題を抱えています。
中でも、最も一般的な方法が、家族、つまり親族内での事業承継です。
しかし、実際に承継を行うには多くの準備と手続きが必要であり、とくに税制面には留意が必要です。
本コラムでは、家族への会社の承継方法や税金対策などを紹介します。
家族承継のメリットと留意点
家族内で事業を承継するメリットは、スムーズな承継を実現しやすい点にあります。
経営者と後継者が親子であれば、社員や取引先からも受け入れられやすく、外部から後継者を迎えるよりも混乱が少ないケースが多いです。
また、相続や贈与で株式を移転しやすく、税制上の優遇措置も活用できます。
一方で、親族間だからこそ発生しやすいトラブルもあります。
たとえば、「誰が後継者にふさわしいか」について家族内で意見が分かれたり、相続時に他の相続人との間で不公平感が生じたりすることも少なくありません。
そのため、感情的な衝突を避けるためにも、早めに承継計画を立てて、家族間で話し合いを重ねておくことが重要です。
会社承継の2つの側面:経営と資産
事業承継には、「経営の承継」と「資産の承継」という2つの側面があります。
経営の承継とは、代表取締役などの役職や日常的な経営判断を後継者に移すことです。
これには社内外への周知や、取締役会での決議、登記手続きなどが伴います。
一方、資産の承継とは、会社の所有権(株式)を後継者に移すことです。
中小企業では、会社の代表が自社株を保有しているケースが多く、経営権の移転とあわせて株式の承継が必要になります。
この株式移転には、主に「相続」「贈与」「売買」の3つの方法があります。
株式移転の3つの方法
株式を後継者に譲渡する方法である「相続」「贈与」「売買」について、それぞれの特徴と留意点をみていきます。
まず「相続」は、経営者の死亡時に自社株式が後継者に移転する方法です。
この場合、経営者自身が株式の移動を確認できないため、生前に遺言や民事信託などを活用しておくことが重要です。
また、他の相続人とのトラブルを防ぐためにも、遺産分割の方針を明確にしておく必要があります。
「贈与」は、経営者が存命中に自社株を後継者に譲渡する、生前贈与の形で行われます。
この方法では、株式が後継者に確実に移転されたことを経営者自身が確認できるため、経営の引継ぎがより計画的に行えます。
ただし、贈与税の負担が発生するため、事前に税務上の対策を講じておくことが望まれます。
「株式売買」は、後継者が株式を買い取る形で経営権を取得する方法です。
これは一般的に贈与税や相続税を回避できますが、一方で、後継者に十分な買い取り資金が必要となる点に注意が必要です。
株式の承継と税金対策
会社の所有権を後継者に渡すには、株式の移転が不可欠です。
しかし、自社株の評価額が高い場合、贈与税や相続税の負担が大きくなる可能性があります。
そのため、事前に株価の引き下げ対策(利益剰余金の活用など)を行うとともに、税務上の制度を活用することをおすすめします。
とくに中小企業向けに整備されている「事業承継税制」は、要件を満たすことで納税が猶予され、一定条件を満たせば最終的に免除されることもあります。
この制度を上手に活用すれば、大きな節税効果が得られ、承継のハードルを大幅に下げることが可能になります。
事業承継税制の活用
事業承継税制は、非上場の中小企業の株式を後継者が取得した場合において、贈与税や相続税の納税が猶予・免除される制度です。
この制度には、「一般措置」と「特例措置」の2種類があります。
中でも、2018年の税制改正で導入された「特例措置」は、2027年12月末までの期間限定で、贈与・相続のいずれの場合でも株式の100%について納税猶予を受けることができます。
また、雇用の維持要件が緩和されたり、親族外の後継者にも適用可能となったりなど、従来の制度よりも柔軟性が高く利用できます。
ただし、制度を利用するには、事前に「特例承継計画」を都道府県に提出し、承認を受ける必要があります。
承継後も継続的な報告義務があるため、制度の詳細をよく理解したうえで、専門家のサポートを得ながら進めることが重要です。
なお、上記の制度内容は2025年6月時点の情報となります。
まとめ
家族に会社を承継するには、「経営」と「資産」の両面から計画的な準備が求められます。
株式の移転には「相続」「贈与」「売買」の3つの方法があり、それぞれに税務や実務上の特徴があります。
また、事業承継税制などの制度を活用することで、税負担を軽減し、円滑な承継が実現しやすくなります。
事業承継について不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
BASIC KNOWLEDGE
-

事業承継は早目の対策...
◆事業承継は早目の対策が重要!経営や事業の承継というのはすぐにできるものではありません。円滑な事業継承を実現するのは、早めの対策が非常に重要です。事業経営を行っておられる場合は、問題を後回しにせずに是非早目にお問合せ下さ […]
-

賃貸住宅の建築
賃貸住宅を建築されると、相続税を計算する上でその土地は「借地権割合×借家権割合」の控除をすることができ、また、貸家は「借家権割合」の控除 をすることができ、財産の評価額が下がるため相続税の節税効果が生じます。賃貸住宅を建 […]
-

相続税いくらまでなら...
相続が発生すると、相続財産の規模によっては相続税が課されることがあります。 しかし、一定の基準以下の財産であれば相続税の申告は不要です。 今回は、相続税がいくらまでなら申告不要なのか、その基準や計算方法について詳しく解説 […]
-

事業承継税制とは?
中小企業の多くが経営者の高齢化と後継者不足という課題に直面しています。事業を次の世代に引き継ぐ際、相続税や贈与税の負担が大きな障壁となるケースも少なくありません。こうした中、税制面から事業承継を後押しする「事業承継税制」 […]
-

相続税においての基礎...
相続税には、課税の対象となる財産から一定額を差し引く「基礎控除」という制度があります。この控除額によっては、相続税の申告そのものが不要になることもあります。本記事では、基礎控除の概要や計算方法、注意点について詳しく解説し […]
-

税務調査されるケース...
◆課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースは特に注意特に、課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースについては、被相続人の自宅に行って調査(臨宅調査)があります。臨宅調査は、通常、申告・納税した年または […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
年間120件の相続相談をこなす『相続特化型』税理士事務所です。
ご安心してお問合せ下さい

-
- 所属団体
- 東京税理士会神田支部
-
- 経歴
-
1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
事務所概要
OFFICE
| 事務所名 | 税理士法人早川・平会計 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田司町2-10安和司町ビル2F |
| 電話番号 | 03-3254-2171 |
| FAX番号 | 03-3254-2174 |
| 受付時間 | 9:00~18:00 (ご予約により時間外対応可) |
| 定休日 | 土・日・祝 (ご予約により休日対応可) |
| URL |