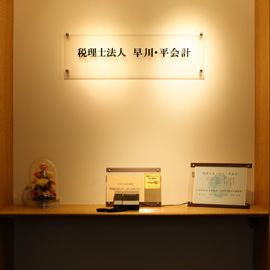事業承継税制とは?
中小企業の多くが経営者の高齢化と後継者不足という課題に直面しています。
事業を次の世代に引き継ぐ際、相続税や贈与税の負担が大きな障壁となるケースも少なくありません。
こうした中、税制面から事業承継を後押しする「事業承継税制」が注目されています。
本記事では、法人版事業承継税制の概要やメリット・デメリットなどについて紹介します。
制度の基本的な仕組み
事業承継税制は、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税が猶予・免除される制度です。
この事業承継税制には、「個人版」と「法人版」の2つが存在します。
「個人版」は不動産賃貸業など個人事業者の事業用資産の承継を対象としており、一方、「法人版」は非上場の中小企業の株式の承継を対象としています。
非上場企業の自社株は、現金のように簡単に処分できる資産ではないにも関わらず、高い評価額がつく場合があります。
そのため、税負担の大きさが後継者にとって大きなリスクとなることがありました。
この制度を利用すれば、そうした納税のための資金調達の負担を軽減することができ、安心して事業を継続するための環境が整います。
ただし、制度の利用にはさまざまな条件があり、先代経営者が筆頭株主であることや、後継者が会社の役員に就任していることなどが求められます。
一般措置と特例措置の違い
事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があります。
「一般措置」は以前から存在する制度で、総株式数の最大3分の2まで納税猶予が認められるものです。
一方、「特例措置」は2018年度の税制改正によって創設されたもので、2027年12月31日までの期間限定の制度です。
この特例措置では、贈与・相続のどちらのケースにおいても、対象株式の最大100%が納税猶予の対象となります。
また、雇用維持要件も緩和され、従来の「平均80%以上の雇用維持」という厳しい条件から、努力義務へと変更されました。
さらに、一般措置は一定の親族への承継に限定されるのに対し、特例措置は親族外の後継者にも適用可能です。
複数の株主から株式を引き継ぐ場合でも利用できるなど、より柔軟な制度設計となっています。
ただし、制度を利用するには、あらかじめ都道府県庁へ「特例承継計画」を提出し認定を受ける必要があります。
制度活用のメリット
事業承継税制を利用する最大のメリットは、相続税や贈与税の大幅な軽減です。
事業承継の際には、通常、自社株の評価額に基づいて多額の相続税や贈与税が課されます。
しかし、事業承継税制を活用すれば、その税金の納付が猶予されたり、一定の条件を満たせば免除されたりするため、後継者は株式を売却したり多額の資金を用意したりすることなく、スムーズに事業を引き継ぐことができます。
制度活用のデメリット
一方で、事業承継税制には留意すべきデメリットも存在します。
制度の適用には税務署の厳しい審査があり、適用後も都道府県や税務署への定期的な報告が求められるなど、手続きが煩雑です。
さらに、納税猶予が認められた後でも、代表者の退任や株式の譲渡、同族関係者の議決権割合の変化、会社の解散など、一定の「取り消し事由」に該当すると、猶予されていた税金に加えて利子を含めた一括納付が求められます。
一括納付となった場合は資金繰りに大きな影響を及ぼすため、制度の利用にあたっては専門家の助言を受けながら慎重に対応することが重要です。
手続きの流れ
事業承継税制の手続きには、いくつかのステップを踏む必要があります。
特例承継計画の提出
まず、特例措置を利用する場合は、事前に都道府県へ「特例承継計画」を提出しなければなりません。
この計画の提出期限は、2026年3月31日です。
認定書の取得と申告
承継が実際に行われた後は、都道府県に対して事業承継税制の申請を行い、認定書の交付を受けます。
続いて、税務署にその認定書を添付して申告を行うことで、正式に納税猶予が適用されます。
納税猶予後の継続手続き
納税猶予の適用後も、継続的な手続きが求められます。
たとえば、毎年1回、都道府県には「年次報告書」を、税務署には「継続届出書」を提出しなければなりません。
これらの報告義務は、制度の要件を引き続き満たしているかを確認するために必要です。
なお、「継続届出書」は5年経過後からは、3年に1回の提出となります。
免除の可能性があるケース
贈与の場合に先代経営者が死亡したとき、あるいは相続の場合に後継者が死亡したときなどは、その時点で納税が猶予されている税額の全部または一部について、納付が免除される場合があります。
まとめ
事業承継税制は、中小企業の存続と発展を支える重要な制度です。
とりわけ、法人版の特例措置は税負担を大幅に軽減し、スムーズな事業承継を行う上で大きな意義を持っています。
一方で、制度の適用には複雑な要件と慎重な対応が求められ、専門家との連携が重要となります。
なお、上記の制度内容は2025年6月時点の情報となります。
お悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
BASIC KNOWLEDGE
-

相続時精算課税制度の...
相続時精算課税制度は、生前贈与を活用する際に利用できる税制のひとつです。贈与税の負担を軽減しつつ財産を移転できる一方、注意点やデメリットもあるため、制度を正しく理解して活用することが重要です。今回は、相続時精算課税制度の […]
-

相続手続きの流れ
◆相続が開始した際の相続手続きの流れ・遺言書の有無の確認遺言書が残されていないかを確認します。※遺言書がある場合には家庭裁判所で確認を受けてから開封します。・相続する財産と債務の確認まずは被相続人がどんな財産と債務を持っ […]
-

事業承継は早目の対策...
◆事業承継は早目の対策が重要!経営や事業の承継というのはすぐにできるものではありません。円滑な事業継承を実現するのは、早めの対策が非常に重要です。事業経営を行っておられる場合は、問題を後回しにせずに是非早目にお問合せ下さ […]
-

事業承継税制はどんな...
会社を後継者へと引き継ぐ事業承継ですが、黒字であっても事業承継ができずに廃業となってしまうことがしばしばあります。円滑な事業承継を妨げている要因はさまざまです。例えば少子高齢化によってそもそも後継者となる者がいないことも […]
-

生前贈与
相続税対策として、比較的実行しやすいのが「生前贈与」です。生前贈与による相続税対策は、1回あたりの効果は小さい ものの、毎年積み重ねて行うことでその効果は累積していきます。そのため、早い時期から計画的に実行していただきた […]
-

相続税いくらまでなら...
相続が発生すると、相続財産の規模によっては相続税が課されることがあります。 しかし、一定の基準以下の財産であれば相続税の申告は不要です。 今回は、相続税がいくらまでなら申告不要なのか、その基準や計算方法について詳しく解説 […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
年間120件の相続相談をこなす『相続特化型』税理士事務所です。
ご安心してお問合せ下さい

-
- 所属団体
- 東京税理士会神田支部
-
- 経歴
-
1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
事務所概要
OFFICE
| 事務所名 | 税理士法人早川・平会計 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田司町2-10安和司町ビル2F |
| 電話番号 | 03-3254-2171 |
| FAX番号 | 03-3254-2174 |
| 受付時間 | 9:00~18:00 (ご予約により時間外対応可) |
| 定休日 | 土・日・祝 (ご予約により休日対応可) |
| URL |